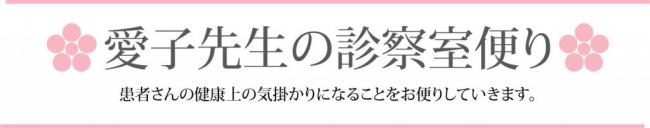
精神科医Marikoの視点から
海外在住日本人向けに心理カウンセリングを提供している日本の精神科医/心理士の首藤まり子です。愛子先生と心身の健康維持に役立つ情報を発信しています。
前回は「ウェルネス」という新しい健康概念に注目しましたが、今回はその実践方法の一つとして、マインドフルネスの基本と、誰でも簡単に試せる5-4-3-2-1グラウンディング法についてご紹介します。
マインドフルネス(Mindfullness)の基本的な考え方
私たちが日常感じる不安や悩み(「これから何が起こるか」「過去の失敗」など)を、「ただの思考」として捉え、反応せずに客観的に観察する練習方法です。ただ「そう感じている自分」を客観的に認識することで、思考や感情に振り回されることなく、冷静で集中力を維持することが可能になります。
例えば通勤中にイライラするような出来事があった場合:マインドフルネスを実践することで、「今の自分はイライラしている」と自己認識し、一歩引いて状況を観察することができます。これにより、感情に流されず冷静に対応する余裕を持つことができます。
実践ガイド:5-4-3-2-1グラウンディング法
このシンプルな方法は、急な感情の高ぶりを感じた際に心を落ち着けるのに役立ちます。短時間(数分以内)でどこでも実践可能で、繰り返し練習を重ねることで、より迅速に感情をコントロールし、不安を軽減する効果があります。
【具体的な手順】
- 見えるもの5つ: 5つの物を見て、色、形、素材などに注意を向ける(例:椅子、テーブル、窓、植物、絵画)
- 聞こえる音4つ: 4つの音に耳を傾け、それぞれどのように聞こえるか、その距離感や高低を感じ取る(例:エアコンの音、鳥の鳴き声、遠くの交通音、時計の秒針)
- 触れているもの3つ: 自分の身体が直接触れている3つの物に意識を向け、感触を意識する(例:衣服の質感、足の下の床の感触、空気の流れ)
- 匂い2つ: 空気中の2つの匂いを嗅ぎ、どのような匂いかを識別する(例:コーヒーの香り、書籍の匂い)
- 味わっているもの1つ: 口の中の味や、最近食べた物の味を思い出す(例:口に残る朝食の味)
マインドフルネスの効果
5-4-3-2-1グラウンディング法のような定期的なマインドフルネスの実践は、日々のストレスを効果的に管理するのに役立ちます。それは結果として精神的な健康の向上につながり、全体的な幸福感を高めていきます。
まとめ
マインドフルネスは「心の筋トレ」とも言われたりします。日常生活で起こるさまざまな出来事や感情に対して、無防備に反応するのではなく、意識的に注意を払い、様々な感情が湧き上がる自分自身をありのままに受け入れる訓練をしていきましょう。次回は、ウェルネスの他の実践方法について解説していきます。お楽しみに!
MARIKO COUNSELLING
Mariko Shudo 精神科医/産業医/公認心理士(日本)
・MARIKO’s Wellness (HP)
・カウンセリング詳細/予約
・お問い合わせ E: mariko@doctoraiko.com
 |
 一人ひとりに向き合った医療を提供 一人ひとりに向き合った医療を提供
富田愛子 Dr. Aiko(Tiarni)Tomita
W: doctoraiko.com.au
E: admin@doctoraiko.com 診療場所: MIDTOWN MEDICAL CLINIC メンタルヘルス サポートとして、経験豊富な精神科医首藤まり子先生が、対面/オンラインの両方でカウンセリングをしています。 |

